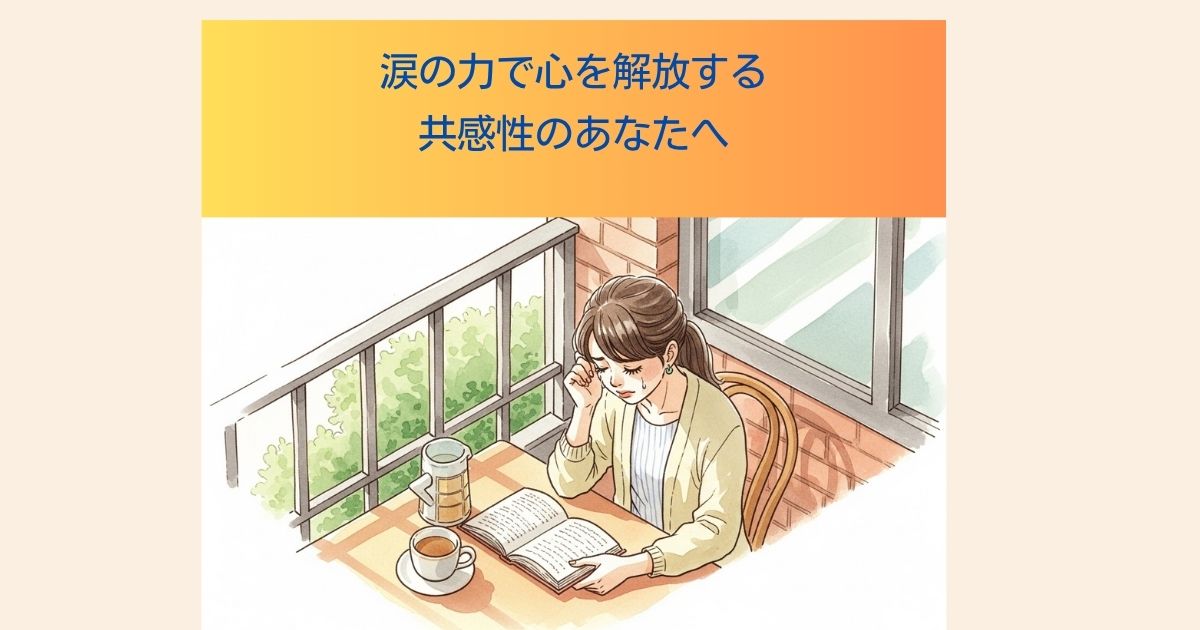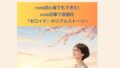涙が溢れることには、ちゃんと意味がある。
日々、人の気持ちや空気をすぐに感じ取り、自分の感情も抑えがちになってしまう「共感性」が高いあなたへ。
今日は、涙とゆっくり向き合い、「心の声」に耳を澄ます、その小さな時間についてお話しします。
涙がもたらす癒しとは
涙を流すことは、心身のストレスを和らげてくれる自然の働きです。
感情が高ぶったときに溢れる涙には、「デトックス効果」があることがわかっています。
例えば、悲しいとき・感動したとき、じわりと溢れる涙にはストレスホルモン(コルチゾール)を体外へ排出する役割があるそうです。
泣いたあと、「なんだかスッキリした」と感じる経験はありませんか?
それは自律神経がストレス状態(交感神経優位)からリラックス状態(副交感神経優位)へ切り替わるから。
言い換えれば、眠った後のような深いリラックスに心が包まれるのです。
感情の解放としての涙
涙は、感情の抑えすぎをやわらげてくれる“安全弁”のようなもの。
普段、誰かの気持ちを優先しすぎて、自分の本音に気づかないまま過ごしてしまいがちな共感性タイプ。
ですが、感情を抑圧し続けると、心にも身体にも負担がかかります。
そんなときこそ、涙として気持ちを外に流してあげることで、心がほっと休まり、再び前を向くエネルギーが湧いてきます。
「心の声」に気づく、涙の時間
涙がこぼれる瞬間、それはあなたの心の奥から、「これが本当に感じていることだよ」と教えてくれているサインです。
たとえ言葉にできなくても、涙というカタチで自分の“本当”と向き合えている証。
泣くことができる人は、決して弱い人ではありません。
むしろ、感情を大切にできる人の美しさなのだと思います。
共感性が生みやすい「心のためこみ」をほどく、五感を使った感情の味わい方
共感性が高い人は、人の気持ちを感じ取りすぎて、自分の感情を無意識にためてしまうことも多いもの。
だからこそ、喜怒哀楽を五感を通してしっかり感じることが大切です。
例えば、嬉しいときに美味しいものを味わい、悲しいときに優しい音楽に耳を傾ける。
怒りが湧いたときには深呼吸して風の匂いや冷たさを感じる。
そうやって五感で「今の気持ち」を味わうことは、感情の流れをつくり、ため込みを防ぐやさしいセルフケアになります。
涙とやさしく向き合うコツ
- 泣くことを否定しないこと。「また泣いちゃった」と自分を責めず、「いま素直に心の声を聴けている」と認めてあげましょう。
- 涙を流した日には、心地よい飲み物や音楽で自分をいたわる時間をつくるのがおすすめです。
- 信頼できる人に話を聞いてもらうと、涙も自然と溢れやすくなります。「話すと涙が出ちゃうかも」と予め伝えておくと、やさしく受け止めてくれるはずです。
涙で心をゆるめることは、自分自身へのギフト。
感じるままに涙し、さらに五感で感情を味わうそのひとときを、どうか大切にしてください。
きっとその涙のあと、あなたはまた自分らしく歩きだせるはずです。
最後までお読みいただきありがとうございました。