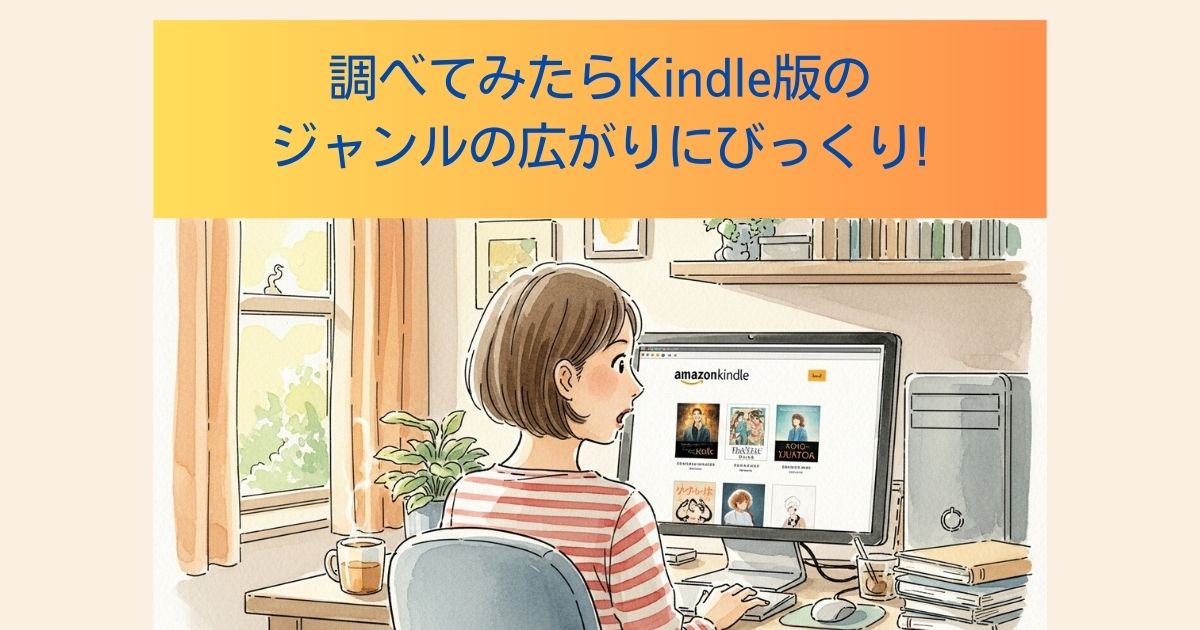不思議な疑問がわきましたので、早速調べてみたらわかったことがありました。
他の人にとっても興味深い話かと思ったのでシェアしたいと思います。
なんの話かというと、Amazonで本を出版するとき、このジャンルに入れますと決めて登録するんですよね。
今回、人生初のKindle出版した『消された世界の存在証明』の場合、「経済・社会小説」と「SF・ホラー・ファンタジー」と「倫理学・道徳」に登録したんです。
しかし、ふと見てみたら順位は下の方なんですが、「文学・評論」とか「人文・思想」のジャンルにも不思議なことに出ていたんです。
なぜジャンルをまたいで本の順位が上がるの?
でも、出版後にAmazonやKindleのシステムが自動的に、本の内容や読者の反応を分析して、ほかの関連ジャンルでも「この本は合う!」と判断することがあるそうなんです。
- Amazonは、読者さんたちがどんな検索をして、どんな本を読んでいるかを常に見ています。
- その読者の動きや、レビューやキーワードなどの内容から、本の「別の顔」も見つけてくれるのです。
- だから、最初は登録していなくても、別のジャンルの棚にも本が並ぶことがあるんです。
つまりどういうこと?
「この本は最初に決めたジャンルだけでなく、関連する他のジャンルでもおすすめできる価値があるよ」というAmazon側の判断が働いているということです。
これは、読者の興味や本の内容を広くとらえた動きなので、むしろ嬉しいこと。
より多くの人に届くチャンスが増えている状態なんですね。
まとめ
出版ジャンルは「本の入り口」ですが、読者やAmazonのシステムが本の魅力をたくさん見つけていってくれる。
だから、出版ジャンル以外でも順位が上がりやすくなる。これは自然で良い現象なんだなぁと思いました。
これは自分で実際出版したからことわかったことです。
実体験がやっぱり学びにつながるなぁとしみじみ思いました。
最後までお読みいただきありがとうございました。